投稿日時: 2015/01/08
 図書館管理者
図書館管理者
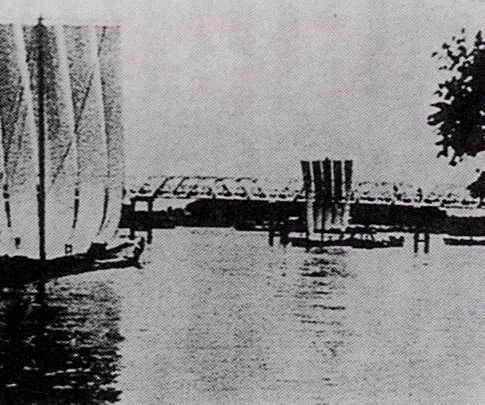
慶長10年(1605年)に矢作新川ができて、矢作川の本流になり、矢作川の水運は、川船により盛んになりました。
矢作川を上下する川船は、数多くの物資を積んで岡崎に送られました。また、ある物は上流の古鼠(豊田市)や巴川の九久平、平子(豊田市)で陸揚げされてから、馬に積まれ足助へ、また、馬に引き継がれ信州方面に運ばれました。矢作川をのぼる荷物は鉄、綿、米、麦、大豆、味噌、干鰯、樽、荒物、小間物、塩、干魚、魚の〆粕、鋳物、土管、しょう油、酢などでした。
矢作川を下るものは材木、竹、石、炭、薪、たばこなどで、信州や上流の山地の材木や竹材などは筏に組んで下りました。また、上流からの年貢米などは川船で下り、鷲塚、平坂湊から江戸へ運ばれました。
特に、三河湾沿岸の大浜、成岩、饗庭で生産された塩は、平坂や大浜から川船で途中の岡崎にある塩座を経由し、巴川の平古土場まで送られ、そこから馬で足助の塩問屋へ送られ、ここで各地の塩を混合して、七貫俵に詰め替えられました。これを「足助なおし」とか「塩ふみ」といいました。これから足助塩として馬1駄、4俵付きで、三州馬、中馬によって武節、根羽を経て信州に運ばれました。これが、「塩の道」で、三河と信州を結ぶ重要な運輸交通路でした。
下流の地域では、矢作川の清流は、良好な地下水となり、新田の米を使い、酒の醸造が行われ、酒は大浜湊、平坂湊から江戸へ送られました。ほかに、焼酎、みりんの醸造も行われました。なお、掘抜き井戸は冬暖かく、夏は冷たい水が吹き上がっていました。
碧南市広報2001年8月11日号より

